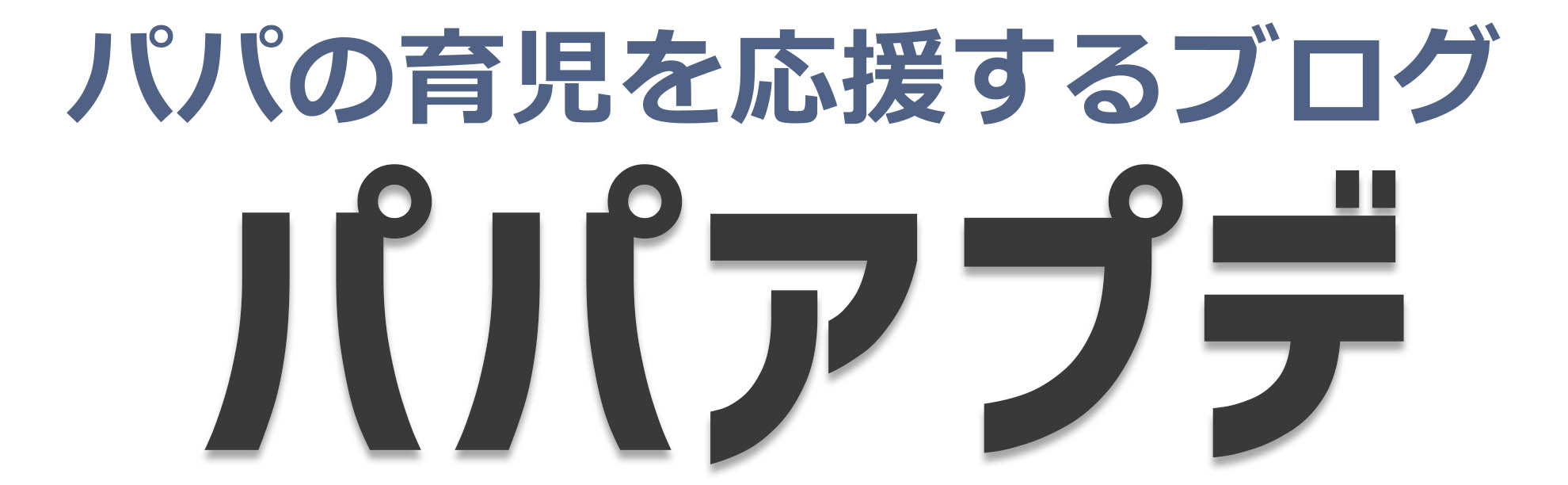この記事では、男性が育児をするメリットを22個紹介します。
今回紹介する内容は、私の実体験であったり私がメリットだと思うことを調べ直して共感した内容を書き出したものです。
以下のような方の参考になれば幸いです。
- これから子供が生まれてくる方
- 育休を取得中または取得予定の方
- 育児で悩まれている方
- 育児をする目的がわからない方
それでは行ってみましょう。
私について
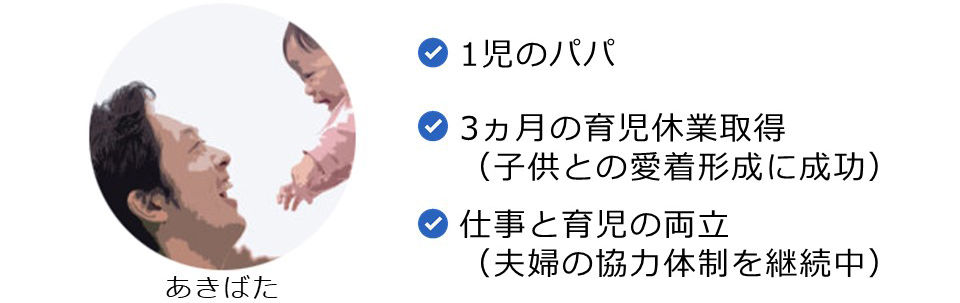
子供が生まれてすぐに育休を取得。現在は仕事に復帰して育児との両立を図っています。この記事はそんな二足のわらじをはいている人の視点でお伝えします。
パパのメリット

最初にパパのメリットを15個紹介します。
育児をするとパパ自身に有益なことが起きるんだと感じていただければ幸いです。
1.親の自覚が芽生える
育児をすることで親の自覚を持ちやすくなります。
ママは妊娠期間があるので自然な流れで親の自覚を持てるようになりますが、パパは親になったと実感できる機会が少ないので親の自覚を持つまでに時間がかかると言われています。
懸命にお世話をして子供と密接な時間を過ごすことで、パパはだんだんと親の自覚を持てるようになっていきます。

子供が生まれてすぐに親の自覚を持てるわけではないので焦らなくても大丈夫です。
2.子供と愛着関係が築ける

育児に時間を割き、スキンシップやお世話を続けることで子供はパパのことを信頼するようになります。
子供から信頼されることでパパの自尊心が満たされ、父子の間に絆が生まれます。
愛着関係とも呼ばれるこの絆は、子供が健全に成長していくためになくてはならない親子のつながりです。
ママだけでなくパパとも愛着関係を築くことで、子供の成長にさらにポジティブな影響を与えられます。

最初はパパになついていなくても、お世話を続けるうちにパパを信頼するようになります。
愛着関係については下記の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご一読ください。
3.自分を必要としてくれる人に全力で向き合える
人は皆どこかで「誰かから必要とされたい」と願っているものです。そして、我が子ほど自分のことを必要としてくれる人はいません。
特に乳幼児期は親である自分にぴったりとくっついてきて、泣いたり怒ったりしながらさまざまな要求をしてきます。
そんな我が子に全力で向き合うことで誰かから必要とされたいという欲求が満たされていきます。
全力で向き合えるチャンスは今だけ
要求の多さにうんざりすることもありますが、子供が親のお世話を必要としてくれるのは生まれてからの数年間だけです。
この貴重な機会を逃さずに子供と向き合える点もパパが育児をするメリットの一つです。

お世話の仕方がわからない方は、ミルクをあげることから始めるといいと思います。
4.家庭内に役割が持てる=家庭に居場所がある

育児をすることで、家庭内に居場所を確保できます。
子供が生まれるとこれまでの生活とは一変して子供中心の生活が始まります。
家庭内は家事育児のタスクで溢れかえるようになり、ママはその対応に追われていきます。
リビングは大人がくつろぐ場所から育児をする場所へと変わるので、そこでパパがゴロゴロしていたら白い目で見られてしまうかもしれません。
パパが家事や育児をして家庭内に役割を持つことで、自然な形で居場所を確保できます。
5.ママの置かれている状況への理解が深まる
育児の大変さを体験することで、ママの置かれている状況への理解が深まります。
ワンオペ育児や夜泣き対応、子供を連れてのお出掛けなど育児にはさまざまな苦労があります。
パパが育児をすることでこういった苦労を身をもって知ることができ、ママが置かれている状況への理解が深まっていきます。
育児の大変さを知るほどに、「ママ1人に任せているわけにはいかない」という気持ちがわいてくるはずです。

パパのワンオペ育児ができれば、ママのリフレッシュ時間を確保できます
6.人とのつながりの大切さを再確認できる
育児という新しいジャンルに取り組むことで、いままで見えていなかったことが目に付くようになります。
公園を毎日清掃してくれる人やバリアフリー化された街をみて、自分が多くの人に助けられながら生きていることを実感できますし、
電車で席を譲ってもらえたりエレベータを開けてもらえたりと、さまざまなやさしさに触れることで人とのつながりの大切さを再確認できます。
7.自分のアイデアを実現できる

仕事で自分のアイデアを実現できると充実感や自尊心が満たされますが、パパは育児でも自分のアイデアを実現できます。
子供は日々成長していくので、月齢に合わせて食事や遊び方を変えていく必要があります。
また、子供が走り回ったり段差をよじ登れるようになるとケガをする危険性が増えるので、室内環境を整えていく必要もあります。
ママ1人でこういった変化にすべて対応することは困難ですから、パパのアイデアが求められる機会は日常的にあります。
自分が提案したアイデアが良い結果につながるとうれしいですし、自分のアイデアを必要としてくれる環境で暮らせること自体がパパのメンタルに良い影響を与えてくれます。

室内環境を整えたり動線の効率化を図ることはパパの得意分野です。
8.時間の使い方がうまくなる

育児をすると時間の使い方がうまくなります。
限られた時間の中で家事・育児・仕事をするので、無駄な時間を省く必要があるからです。
仕事をできるだけ早く終わらせるように努めたり、惰性で毎晩お酒を飲むこともなくなるので生活にメリハリが生まれます。
9.自分の機嫌を自分で取れるようになる
育児をすることで「自分の機嫌を自分で取る」スキルが身に付いていきます。
育児中、自分の機嫌が良いと子供が何をしてもわりと許せます。反対に不機嫌だと子供の行為を正そうとします。
親の気持ちひとつでお世話の仕方は変わりますが、ほとんどの場合親の機嫌が良い方がうまくいくものです。
育児に慣れてくると、自分の機嫌が良い方が円滑にお世話が進むことがわかってくるので、自然と「自分の機嫌を自分で取る」ようになっていきます。
社会生活でも役立つスキル
この「自分の機嫌を自分で取る」スキルは社会生活でも大いに役立ちます。
多少の不満であれば自分で処理できるようになるので対人関係がラクになりますし、不用意に会社への不平不満を漏らして社内の空気を乱すようなこともせずに済みます。

最初から無理して上機嫌でいなくても大丈夫です。私も育児を始めたころはイライラしやすかったです。
10.夫婦仲が良くなりやすい
パパの育児参加は夫婦関係に良い影響を与えます。
子供が生まれると生活が激変するので夫婦関係がこれまでとは変わっていきます。
パパが育児に関わることで「育児」が夫婦共通の話題になるのでコミュニケーションが取りやすくなります。
コミュニケーションが増えれば互いの気持ちを伝え合う機会も増えるので、夫婦のすれ違いが起きにくくなるメリットがあります。
また、夫婦で力を合わせて育児に取り組むことで、夫婦の間に新しい仲間意識が芽生える可能性もあります。
11.人間らしさをより深く理解できる

育児をして我が子と密接に関わり合うことで人間らしさをより深く理解できます。
子供は感情の赴くままに行動するので理屈が通用しません。
そんな子供のお世話をするときは気持ちを受け止め理解を示し続けることが大切です。
気持ちを受け止めてほしいのは子供だけではない
私たちは普段、言葉が通じる相手と理性的にコミュニケーションをしているので、感情の赴くままに行動する相手と関わり合うことはありません。
ただ、大人であっても理屈では割り切れない感情的な側面を持ち合わせているものです。
育児をして子供の感情の浮き沈みに付き合っていると、「人って結局、自分のわがままや欠点を許容してくれる人が好きなんだよね」という人間らしさを再確認できます。
こうした経験や理解は人の気持ちを受け止める大切さを見直すことにつながり、それは仕事や人付き合いの場面でも多いに役立ちます。

会社組織も理屈ではなく感情で動いているところがありますよね。
12.子供の成長していく姿から刺激をもらえる
親の背中を見て子は育つと言いますが、育児に取り組むことで親も子供からたくさんの刺激をもらえます。
子供は毎日失敗を繰り返しながら新しいことに挑戦しています。
失敗してもニコニコ笑ってどんどん新しいことを吸収していく我が子の姿を見ていると、「自分も我が子を見習って何かに挑戦しなければ」と思えるようになります。
13.オキシトシンが分泌する
育児をすることで、パパの体内にオキシトシンが分泌されます。
オキシトシンは人間の体内で作られるホルモンの一つです。
通称「愛情ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンは、妊娠中や育児中のママに多く分泌されることで知られています。
そんなオキシトシンには以下のような効果があります。
- 幸せな気分になる
- 他者への信頼感が高まり寛大になる
- ストレス耐性が高まる
- 学習意欲や記憶力が向上する
自分は愛されていると感じられ、他者に対しては親密な関係を築きたいと思うようになります。
まさに育児にうってつけなホルモンですが、パパも懸命に育児をしていればオキシトシンの分泌量が増えることがわかっています。
男性は女性と同様に、育児をすることで身体の機能を変えることができるわけです。
オキシトシンのもう一つの作用
一方、オキシトシンは他者への攻撃性を高める効果もあるようです。
育児中のママはオキシトシンが多く分泌されているので、パパが育児に非協力的だとパパのことを攻撃の対象とみなすことがあります。
育児をせずに家でゴロゴロしているパパにイライラするママが多い理由は、オキシトシンの影響があるからなのかもしれません。
14.「3歳までに一生分の親孝行をする」

子供は3歳までに一生分の親孝行をすると言われることがあります。
それが事実かどうかはわかりませんが、こういった表現がさせるくらい価値あるものを得られることは確かです。
0〜3歳だと意思疎通がうまくできず、泣いてばかりで親孝行とは程遠いと思われるかもしれませんが、
子供の笑顔や、小さい手で自分の指を握ってくれたこと、寝顔や抱きついて離れなかったことなど一つ一つが忘れられない思い出になっていきます。
パパが育児をすることで、こういった人生の財産になるような思い出を子供と一緒に積み重ねていけます。

「3歳までに一生分の親孝行をする」と表現されるのもうなずけるくらい充実した時間を過ごせます。
15.仕事を見つめなおすきっかけになる
育児をすることで人生の視野が広がるので、仕事との関わり方を見つめ直すきっかけになります。
仕事から得られる充実感や達成感は素晴らしいものです。ただ、仕事がどれだけ充実していようとも、育児から得られる幸福の代わりにはなりません。
家族から必要とされ、助け合いながら一緒に時間を過ごすことで感じられる幸福は、仕事では絶対に得ることができないからです。
何に時間を使うかを見つめ直す
1日は24時間しかありません。私たちの体力も有限です。
その日使えるリソースのすべてを仕事に割くことは立派な選択ですが、別の見方をすると家族との時間を犠牲にして得られるはずだった幸福を手放しているとも言えます。
育児をして人生の視野を広げることで、仕事とどう関わり合うべきかを見つめ直すきっかけになります。
子供のメリット

続いて子供のメリットを3個紹介します。
パパが育児をするだけで子供にさまざまな良い影響を与えます。パパが育児参加する価値の大きさを感じていただければ幸いです。
16.子供の自尊心が高まる
パパの育児は子供の自尊心を高めると言われています。(参考:父親の役割と子育て参加)
自尊心の高い子供はメンタルが安定しやすく、以下のような特徴を持っています。
- 癇癪をおこしにくい
- 物怖じしない
- よく笑う
- 我慢強い
- 会話の反応が早い
パパが早くから育児参加するほど子どもの自尊心は高まりやすく、問題行動を起こしにくくなると言われています。

こんなたくましい子に育ってくれたらうれしいですよね。
17.社会性が向上する
パパが育児をすると子供の社会性が高まります。
子供への接し方は人によってさまざまで、同じおもちゃでもパパとママでは遊び方が違います。
子供はこうした違いをよく見ていて「ママはこのおもちゃを振ったら喜ぶけど、パパは叩いた方が喜ぶ」などと相手によって行動を変えます。
普段からパパママと接することで子供がさまざまな状況を経験することができ、その場に合った対応を学ぶことで社会性が高まっていきます。
18.子供の非認知能力が向上する
非認知能力とは学力テストなどでは計れない子供の人生を豊かにするチカラのことです。
具体的には以下のような能力のことを非認知能力と呼びます。
| 非認知能力の名前 | 具体的な能力 |
|---|---|
| 自己認識 | 最後までやり抜く力、自己肯定感 |
| 意欲 | やる気、集中力 |
| 忍耐力 | 粘り強さ |
| セルフコントロール | 自制心、理性 |
| メタ認知 | 客観的思考、判断力 |
| 社会的能力 | リーダーシップ、協調性、思いやり |
| 対応力 | 応用力、楽観性 |
| クリエイティビティ | 創造性 |
パパが育児をすることでこういった目には見えない能力が伸びると言われています。
特にパパはママと比べてダイナミックな遊び方をするので、それが子供にとって良い刺激になると考えられているようです。
ママのメリット

最後にママのメリットを4個紹介します。
パパの育児参加は家族全体に良い影響があることを感じていただければ幸いです。
19.育児負担をパパとシェアできる
パパが育児をして負担を夫婦でシェアすることで、ママの最低限の健康を維持する手助けができます。
最近は核家族化が進み、夫婦だけで育児をする家庭が増えてきました。
一方で、育児は夫婦二人で協力しても処理しきれないほどのタスクがあります。
また、幼い子供はちょっと目を離している間に危ないことをしている場合もあるので、お世話をしている親は気が休まりません。
こうした育児負担をママ一人で背負ってしまうと、負担の重さから育児ノイローゼになってしまう場合もあります。
パパが育児をして負担を夫婦でシェアすることは、ママの負担軽減につながるだけでなくママの健康維持にも寄与できます。
20.ママが子供から離れてリフレッシュできる
パパが育児をしてママのリフレッシュ時間を確保することで、育児の質が向上します。
休みなく働き続けると生産性が下がるのと同じように、育児もリフレッシュする時間がないと質が下がっていきます。
より良い育児をするためには、親がリフレッシュをして心身の健康を保つことが大切です。
パパが育児をすることでママのリフレッシュ時間を確保でき、ママがしっかりと休めることは育児の質の向上に寄与します。

パパとママが交代でリフレッシュできると、育児へのモチベーションが上がりやすいと思います。
21.相談相手ができる

ママにとって最も身近な存在であるパパが育児をすることで、ママが育児で困ったときの良き相談相手になれます。
子供の性格はさまざまで、引っ込み思案な子もいれば主張が強い子もいます。同じ月齢の子でも一人一人違った個性があります。
そのため、お世話の仕方で悩んだときに友人に相談したりネットで検索しても解決策が見つからないことはよくあることです。
そんなとき、子供の個性をよく知っているパパが育児をしていればママの良き相談相手になれます。
22.喜びを共有できる
育児をしているとうれしくなる瞬間がたびたびあります。
- 離乳食を全部食べてくれた!
- しゃべった!
- おもちゃを渡してくれた!
このように我が子の成長を感じられると何とも言えない幸福な気持ちになります。
パパが育児をしているとこうした喜びをママと共有できます。
育児は大変なことも多いですが、夫婦で協力してときには喜びを共有することで大変な時期を乗り越えるチカラを得ることができます。
まとめ

ここまでパパが育児をするメリットについて書いてきました。
育児って難しいですよね。子供にぐずられて困ってしまうこともよくあります。
育児で困ったときお手本にできる人がいればいいのですが、本来お手本にするべき私たちの親世代は男性が育児をしてこなかったのであまり参考になりません。
お世話の仕方だけでなく、育児を頑張った先に何が得られるのかを同性から聞くことができれば、我々の悩みも少なくなるのかなと思っています。
そんな思いもあって「育児っていいよ!」という記事を書いてみました。
つたない記事ではありますが育児に悩むパパの一助になれば幸いです。